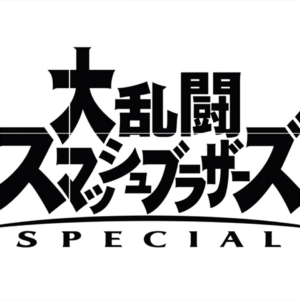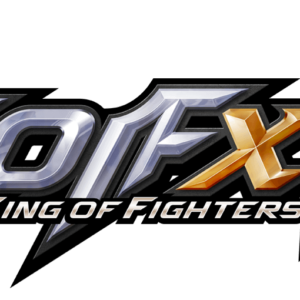eスポーツを学べる高校が増える理由とは?授業で取り組む学校をご紹介!part1
2018年に第1回「全国高校eスポーツ選手権大会」が、開催されました。
その時の参加校は115校。
そして2021年の第4回の参加校は、368校でした。
2019年からは「STAGE:0」という、別の高校生のeスポーツ大会も開催されています。
こちらは2021年の参加校がなんと2145校。
どちらの大会も参加条件は、同じ高校の学生でチームを組むことです。
年々参加校が多くなる理由は、高校のeスポーツ部が増えたからとも言えます。
eスポーツが日本でも浸透してきたのがわかりますね。
また近頃は部活動ではなく、授業としてeスポーツを学ぶ学校も増えてきました。
そこで、今回は以下についてお伝えします。
・なぜeスポーツを授業として学ぶのか
・eスポーツ科を学べる学校
なぜeスポーツを学ぶのかわかれば、eスポーツについての認識が深まりますよ!
目次
eスポーツが学べる学校が増える理由とは?
eスポーツが浸透している海外では、2016年にノルウェーの高校が初めて授業でeスポーツを取り入れました。
現在はヨーロッパの他の国やフィリピン・マレーシアでも、取り入れられています。
海外の高校で取り入れられている理由の一つとして、プロのeスポーツリーグが盛況であり、人材の育成が必要だからと考えられます。
集中力が必要なプロゲーマーが活躍できるのは若い時期だけ。
学校でeスポーツを学ぶ機会があれば早いうちからプロゲーマーの道も開けますし、プロとして活躍すれば学校の知名度も上がります。
また、eスポーツを楽しむためには、高性能なゲーミングパソコンや周辺機器が必要です。
購入者が増えれば経済効果も期待できるため、国がeスポーツを推奨するのも頷けますね。
実は日本で、eスポーツを教育として推奨しているNASEF(ナセフ)という団体があるのをご存じですか?
NASEFとは北米教育eスポーツ連盟(North America Scholastic Esports Federation)の略で、2017年に設立された新しい団体です。
アメリカ合衆国カリフォルニア州を発祥とする教育団体で、eスポーツを通じて若者の成長と可能性を拡げ、多様化が進む社会で活躍する人材の育成を支援することを理念としています。
NSEFは高校生のeスポーツ大会も主宰しており、2022年7月時点の加盟校は377校あります。
全ての学校がeスポーツを熱心に取り入れているわけではありませんが、eスポーツを単なるゲームとしてではなく、青少年の学習ツールの一つとして考えている学校がたくさんあるのがわかりますね。
また日本でも経済産業省がeスポーツ業界の発展を推奨しているため、海外と同様に人材育成のための手段として、学校が増えていると考えられます。
とはいえ、高校の授業として採用するには、「学ぶ」目的が必要です。
次はeスポーツを学校で学ぶ目的をお伝えします。
なぜeスポーツを学校で学ぶのか?
eスポーツを学ぶ目的は主に3つあります。
・インターネットでのマナーが学べる
・チーム活動により社会性が身に付く
・集中力・想像力・戦略や分析などの思考力が伸ばせる
一つずつ解説します。
インターネット上でのマナーや付き合い方が学べる
高校でeスポーツを学ぶ目的の一つは、インターネット上でのマナーが学べることです。
eスポーツはインターネット上で世界各国の人と対戦できます。
高校では国内の学校との対戦が主となりますが、相手が不快になるような言動やプライバシーの侵害に注意しなければなりません。
またeスポーツをしていれば、ゲーム動画配信をする人も多いでしょう。
その場合は、著作権や肖像権についてより注意が必要です。
自分自身の個人情報を守りながら、インターネットを活用するためのマナー全般がeスポーツを通して学べます。
さらに、学校に通いながらeスポーツを学ぶので、生活習慣も乱れません。
「熱中しすぎて1日中ゲームをして朝起きられない」というゲーム中毒にならないように、ネットやゲームとの付き合い方も学びます。
チームワークにより社会性が身に付く
eスポーツを学ぶ目的の2つ目は、チームワークにより社会性が身に付くことです。
高校で学ぶeスポーツは、チーム戦のタイトルとなります。
チーム戦に勝利するためには、チームワークが必要です。
つまり、eスポーツでチームワークを学ぶことで社会性が身に付きます。
高校生の大会は「3対3」や「5対5」といったチーム戦で行われるタイトルです。
2つの高校生eスポーツ大会のタイトルを見てみましょう。
【全国高校生eスポーツ選手権大会】
「リーグ・オブ・レジェンド」「ロケットリーグ」
【STAGE:0】
「リーグ・オブ・レジェンド」「フォートナイト」「クラッシュロワイヤル」「ヴァロラント」(「フォールガイズ」)
チーム戦となると、味方とのコミュニケーションが必要ですよね。
プレイしながら、「どう相手に分かりやすく指示するか」失敗した時も「どうフォローするか」考えなければなりません。
たとえコミュニケーションが苦手だとしてもチームで力を合わせないと勝てないので、自然とお互い意見を出し合うようになります。
好きなゲームでコミュニケーションを取るため、話すのが苦手で自分に自信がなかった人でも自己肯定感がUPできます。
人と関わることで思いやりの気持ちや絆も芽生え、社会性が身に付くのです。
集中力・想像力・戦略や分析などの思考力が伸ばせる
さまざまな能力を伸ばせるのが、3つ目の学ぶ目的です。
eスポーツは、画面を集中して見ていないとゲームの展開にはついていけません。
試合時間は30分以上かかる場合が多く、その間は「画面を見続け」「頭で考え」「メンバーとやりとり」し、「手も動かし」続けます。
しかも自分だけではなく、チーム全体を見て瞬時に判断する力が必要です。
また、eスポーツはチーム戦なので、他のスポーツ同様に戦略を考えなければなりません。
・ポジションはどうするのか
・どう攻めるのか
・攻めに対してどこを誰が守るのか
あらゆるパターンを想定して練習する必要があります。
ゲーム内ではキャラクターの技や道具もさまざまありますので、「チームでだれがどのキャラクターを使用するか」や「対戦相手とのキャラクターの組み合わせ」で、勝敗も変ってきます。
さらに、チームで勝つためにゲーム展開を振り返り、足りないスキルを見極めて部分的な練習も必要となります。
常にチームで勝つことを意識して戦略を考えますので、マーケティングの基礎が学べるとも言えますね。
ここまでeスポーツを学校で学ぶ目的をお伝えしました。
ここからは何回かに分けて、eスポーツを学習のツールとして考えている学校をご紹介していきます。
eスポーツを学べる高校【全日制】
eスポーツを学べる高校は主に、通信制高校や高等専修学校で「eスポーツ専門コース」として学びます。
一方、全日制の普通科高校では専門コースの他、授業の一環としてeスポーツの時間を設けています。
今回は全日制の普通科高校をご紹介しましょう。
全日制の高校でeスポーツを学べる学校は、2つあります。(2022年10月現在)
品川学藝高等学校
https://shinagawa.ed.jp/course1/
日本音楽高等学校として120年の歴史ある学校ですが、2023年に名称を品川学藝高等学校とし男女共学に生まれ変わります。
同時に「eスポーツエデュケーションコース」が新設されました。
学習や教育を促進するための効果的なツールとしてeスポーツに取り組み、「人間力」の育成や大学進学をめざします。
仙台育英学園高等学校
https://www.sendaiikuei.ed.jp/hs/
高校野球で甲子園出場しているため、ご存知の方も多いでしょう。
eスポーツは2018年にパソコン部の一部でスタートし、2019年に部活動として正式に開始しました。
2019・2020年と「全国高校eスポーツ選手権大会」でベスト8に入っています。
部活動と共に、2019年から情報科学コースにて学校設定科目の選択で「eスポーツ講座」が受講できます。
まとめ
今回はeスポーツを学ぶ学校が増える理由と、学べる全日制高校2校をご紹介しました。
学校が増える理由は発展するeスポーツ業界の人材育成があげられます。
そして、学校で学ぶ理由は3つです。
・インターネットでのマナーが学べる
・チーム活動により社会性が身に付く
・集中力・想像力・戦略や分析などの思考力が伸ばせる
全日制高校でeスポーツが学べるのは2校です(2022年10月現在)。
次回は通信制高校や高等専修学校をご紹介いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。